精神科で働いていれば、必ず看護介入するうつ病の患者さん。
うつ病は大きくわけて3つの時期に分かれています。
①急性期
②回復期
③維持期
それぞれの時期で問題点や看護介入の方法にポイントがあります。
今回は維持期でのポイントについてお話していきますね。
急性期看護の記事はこちら
回復期看護の記事はこちら
うつ病の維持期の期間
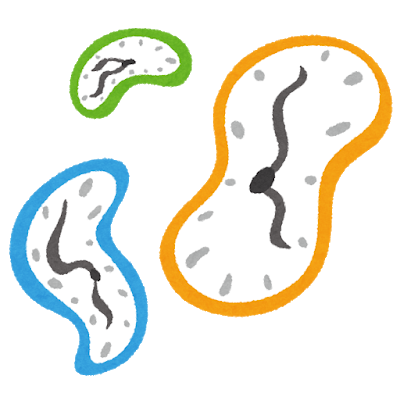
退院目前あるいは退院して数カ月の時期がだいたいの目安になります。
症状がほぼ消失し、病気以前の状態にまで回復している期間のことを指します。
それと同時にストレス耐性が十分に回復している状態ではないことが多い時期でもあることを頭に入れておきましょう。
維持期に生じやすい看護問題

・治療終了後、発症以前の日常生活に戻りやすい
・再発のリスク
維持期における看護目標

・発症前の生活を振り返り、
自分の行動パターンを見直すことができる
・再発の早期発見に努め、
必要に応じてはやめに受診ができる
維持期における看護介入及び看護計画
◎発症時と同じ状況に陥らないようにする
◎周囲の協力を得る
◎服薬、受診の継続
発症時と同じ状況に陥らないようにする

「抑うつや不安につながりやすい考え方のクセ5パターンを紹介」の記事でも紹介したように、うつ病になりやすい考え方のクセというものが存在します。
治療してうつ症状は改善しても、その人の根本の性格をすぐに変えることは難しいです。
そのため、発症時と同じ状況に陥りやすいのです。
入院時から患者さんの性格や行動パターンを認識しましょう。
再発予防のためにも不調のサインを一緒に再確認したり、
うつ病になる状況を意識的に避けるように伝えていきます。
周囲の協力を得る

再発を防ぐためには
本人が自分の不調サインに気づけることが1番です。
ですが、回復期にある患者さんは今までの遅れを取り戻そうと頑張りすぎてしまい、サインを見逃してしまうことも少なくありません。
日常生活での小さな変化に気づきやすい家族にも協力してもらう必要があります。
また、職場に復帰した際に
「なにもしないでいいのでゆっくりしてください」と言われると、
“自分には存在価値がないんだ”と否定されたような気持ちになる場合もあります。
本人の負担にならない範囲で、
しっかりと役割を提供し、肯定的な評価を忘れないようにします。
服薬、受診の継続

うつ病の再発は退院後2~3か月の間に多いと言われています。
そのためこの時期までは基本的に通院や服薬を継続しましょう。
(医師の治療方針に従ってください)
”もう大丈夫”
と自分の勝手な判断で服薬や通院を中断することが一番危険です。
医師の処方通りに服薬すること、
通院するように伝えていきましょう。

病棟では基本的に看護師が薬をその都度渡すようにしています。
自宅退院する患者さんに対しては、退院日や患者さんの状態を見ながら、内服の自己管理ができるような練習を行っていきます 。
退院後、不調を感じた際に“自分でなんとかしないと”と無理をしてしまい、悪化してしまいやすいです。
睡眠に障害が起こった場合、食欲の低下、意欲の低下、など
発症した際に似た症状が出現した場合は躊躇せずに受診するようにも伝えていきます。
まとめ
退院後がメインとなる維持期では
◎発症時と同じ状況に陥らないようにする
◎周囲の協力を得る
◎服薬、受診の継続
などを意識して関わっていきます。
再発が繰り返される場合は生活を見直し、
必要に応じて生活の変更にも取り組んでいきます。
ぽむのおまけ

うつ病の急性期~維持期における看護について記事にしてみました。
気分安定薬で回復していくのはもちろんですが、声掛けひとつで患者さんの精神状態は変化します。
うつ病の人には「頑張れ」と言わないようにしましょう、とよく耳にしませんか?
私も実際に患者さんと関わるとき、つい「一緒に頑張りましょう」と言ってしまいがちなのですが、頑張りすぎてしまった結果、発症してしまうことが多いんです。
頑張らないように頑張りましょう
休憩が今1番必要な仕事です
などの声かけをしています。
患者さんと関わる時間を増やして、患者さんの性格や考え方などの特徴を早期に理解していくことがとても大切だなとしみじみ感じています。
また、再発して再入院される際に「また入院になってしまって、、、」と自分を否定してしまう患者さんが多いです。
再入院してしまった患者さんには、
「入院することが悪いことではないですよ。
必要な時に必要な療養をする場所が病院なので、入院という選択ができたのは良いことです。」
入院=ダメという概念にならないような伝え方をしています。
患者さんとしっかり向き合って、生活や行動を見直せる、精神科ならではの関わりなのかな、と思います。
関わり方はとても難しいのですが、その分やりがいのある分野だなと感じています。




コメント