ECT(電気けいれん療法)看護の後編です!
前回の記事では
・ECTとは何か
・ECTの適応
・ETC実施前と実施直前までの看護計画及び観察項目
についてまとめました。
前編をまだ読んでいない方はこちらから↓↓
今回は!
・ECT中の看護
・ECT後の看護
・ECTの副作用
について説明していきます。
ECT中の看護
医師への報告

当日のバイタルサインや麻酔同意書、心電図の確認をします。
また、精神状態を医師に聞かれた場合は、患者さんの病棟での様子を報告します。
ECTの回数を重ねていく中で患者さんがどのように変化しているかを日頃から観察しておく必要があります。
薬剤や通電時間の記入
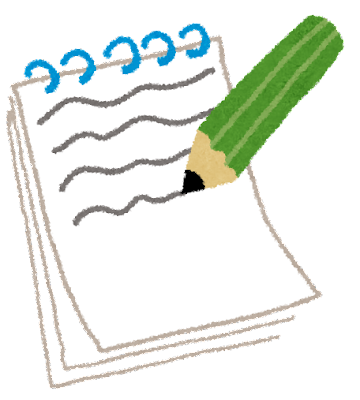
医師が使用した薬剤の量や通電時間を読み上げます。
治療後に医師が記録を残すので、間違えないようにホワイトボードに記載します。
患者の自発呼吸、バイタルサイン確認
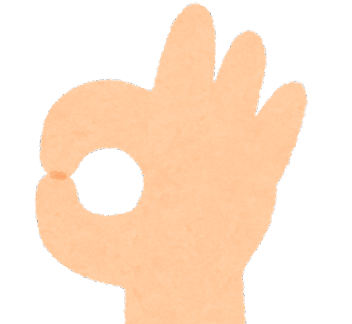
医師とともに患者さんの自発呼吸の有無を確認します。
またバイタルサインも測定し異常がないことを確認しましょう。
ECT実施後の看護と観察項目
バイタルサインに問題がなければリカバリー室へ移動します。
バイタルサインの実施
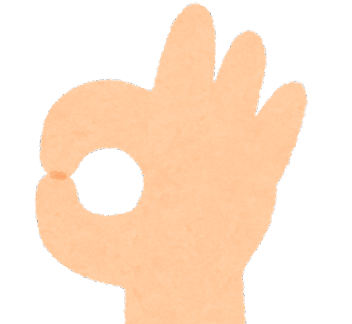
リカバリー室でもバイタルサインを測定します。
このタイミングで患者さんの意識がしっかり戻ることが多いです。
「無事にECTが終わりましたよ。」
「ここがどこかわかりますか?」
などの声かけをします。
・血圧、脈拍、SPO2
・呼吸状態
・心電図の波形(不整脈がないか)
・意識レベル
リカバリー室で5分ほど様子観察し、医師から帰棟の許可があれば帰棟します。
次項からは帰棟後、病棟での看護です。
バイタルサインの実施
帰棟後すぐと帰棟後30分後の2回実施します。
・血圧、脈拍、SPO2
・呼吸状態
・意識レベル
拘束解除の検討

ECT後は、せん妄状態になり興奮して暴れてしまう患者さんがみえます。
点滴の自己抜去予防、酸素マスクを正しく装着してもらうこと、転落リスクを予防する観点からECTを実施する際は拘束を使用することが許されています。
しかし、落ち着いて臥床できていて点滴や酸素マスクの理解も得られているにも関わらず、ベッド上でずっと拘束しているのは患者さんにとって不快ですよね。
そのため、患者さんの体動や安静度の理解度をアセスメントしながら必要に応じて拘束を解除します。
拘束解除を自分の判断で行うことに不安がある場合は必ず先輩に相談してから解除するようにしましょう!
飲水テスト

30分後のバイタルサインで問題なければ、仰臥位からゆっくり端座位になってもらいます。
そして水分摂取をしていただき嚥下に問題がないか確認します。
・覚醒レベル
・呼吸状態の変化
・痰からみの有無
・咽頭部の疼痛の有無
・むせ込みの有無
転倒予防
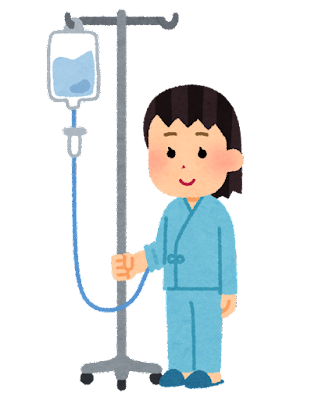
30分後バイタルサイン、飲水テストともに問題なければ、患者さんは自由にしていただいても問題ありません。
ただし、麻酔からの覚醒後はふらつきやすいです。
さらに頭に電気を流す治療であることから、頭痛やめまいを訴える患者さんも多いです。
そのため患者さんにどの程度転倒リスクがあるかをアセスメントしなければなりません。
転倒リスクに応じて
・自室まで付き添う
・リスクが軽減するまで車椅子を貸し出す
・活動が自由になってもしばらく休むように伝える
などの関わりをします。
記録、次回ECTの準備
患者さんの観察がある程度落ち着いたら、記録と次回ECTの準備を行います。
記録に関しては病院で決まったフォーマットがあったのでそれに沿って記録していました。
また、ECT中やECT後に特筆すべき内容があればフォーマットとは別に記録に残して、スタッフ間で情報共有します。

・ECT終了後せん妄が強い
・体動が激しくて拘束解除に○○分かかった
・ECT後ふらつきがあるため付き添いが必要
などの内容を記録することが多かったです。
次回のECT担当看護師が困らないように、必要な物品を補充したり酸素ボンベの残量の確認も忘れずに。
ECT(電気けいれん療法)の副作用

副作用には主に通電直後に出現するもの・覚醒後に出現するものと2種類あります。
通電直後に出現するもの
・血圧上昇または低下
・不整脈
・死亡事故
直後に出現する副作用に関しては医師が対応する場合がほとんどです。
看護師は医師の指示に従い動きます。
麻酔から覚めた後に出現するもの
健忘
私の経験上、最も多い副作用です。
治療前後の事を思い出しにくくなる事がありますが、数時間から数日で回復します。
例)自分の部屋が分からなくなる/食事したことを忘れる
記銘力障害
物覚えが悪くなることがあります。
この副作用が出現した患者さんは少ない印象です。
こちらも一過性で元に戻ります。
頭痛
多くの患者さんにみられました。
これも一時的で、薬剤を使用しなくても改善されることが多いです。
もうろう状態
覚醒後、もうろうとした状態になる事がありますが、これも一過性です。
嘔気
5人に1人程度の割合で出現したような印象です。
程度をみて適切な治療、看護を行っていきます。
(医師への報告、制吐剤の依頼、食事時間をずらすなど)
まとめ
・医師への報告
・薬剤や通電時間の記入
・患者の自発呼吸、バイタルサインの確認
・バイタルサインの実施
・拘束解除の検討
・飲水テスト
・転倒予防
・記録、次回ECTの準備
・血圧上昇または低下
・不整脈
・死亡事故
・健忘
・記銘力障害
・頭痛
・もうろう状態
・嘔気
2回にわたって説明したECT(電気けいれん療法)
少しイメージがついたでしょうか?
私はこのECTを通して、目に見えて精神状態が良くなって退院される患者さんを何人も見てきました。
必ずしも良くなるとは限りませんがECTの効果はすごいと身に染みました!



コメント