精神科で看護介入するうつ病の患者さん。
うつ病は大きくわけて3つの時期に分かれています。
①急性期
②回復期
③維持期
それぞれの時期によって、
問題点や看護介入の方法にポイントがあります。
今回の記事では回復期におけるポイントについてお話していきますね。
急性期看護の記事を読んでからの方が流れを理解しやすいと思います。
まだの方はこちらから↓
うつ病の回復期の期間
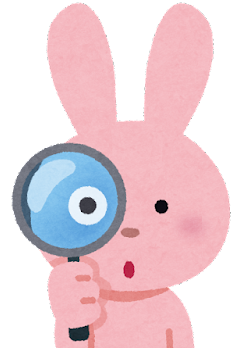
急性期は診断から約3か月が目安でしたね。
回復期は○か月といった目安はなく、
1番辛い症状が軽減し、病状が安定してくる時期をいいます。
回復期の過程で、症状がよくなったり、悪くなったりすることも。
階段をイメージしてもらうとわかりやすいです。
階段を一歩ずつ上るように、少しずつ回復へむかっていくイメージです。
回復期に生じやすい看護問題

病状が安定してきた回復期では、
“はやく復帰したい”
という気持ちが強まる
→焦りを感じる
長い治療期間を経て
“これ以上よくならないのでは?”
→悲観的になる
“休んでしまった分の遅れを取り戻さないと!”
→頑張ってしまう
このような考えになる傾向にあります。
急性期では人と話す気力がなかった方でも、
回復期に移行すると面会ができるようになります。
(精神科の場合は主に家族との面会のみ可能な病院が多いです)
家族(や周囲の人)との関わりが症状に影響を及ぼす可能性も考えられるのです。
回復期における看護目標

・患者さんができることを少しずつ増やすことができる
・少しずつ回復に向かっていることをフィードバックする
・退院後の生活をイメージし、
必要に応じて家族や職場の人との関係を調整する
回復期における看護介入及び看護計画
◎少しずつできることや行動範囲を拡大していく
◎必要に応じて行動や思考のクセを修正する
◎退院後の生活をともに考える
◎家族への説明、必要に応じて職場・学校などの周囲の人に説明する
◎自殺への注意
少しずつできることや行動範囲を拡大していく

基本的な日常生活が自立して行えるようになってきたら、少しずつその他の活動にも目を向けられるように介入していきます。
例えば自室の整理整頓や洗濯など。
もっと細かい例を挙げるとしたら、
朝起きたら自室のカーテンを開ける、など。

いきなりではなく、少しずつで大丈夫です。
患者さんの症状に合わせて、
まずは毎週金曜日に洗濯するように計画したり、
部屋の整理整頓は昼食を食べ終わったら一緒に実施する。
など無理のない範囲から始めましょう。
必要に応じて行動や思考のクセを修正する

他者との関わりが持てるように
作業療法の参加を促す
数人の患者さんで話す機会を作るなど
周囲の出来事や人々に関心を持てるように援助します。
人と関わることで新たなストレスや問題点が発生することももちろん考えられます。
それが看護介入のチャンス。
その問題点を患者さんと一緒に解決できるようにしていきましょう。
私が実際に受け持った患者さんの例をご紹介します。
<回復期にあるAさんは、ほぼ毎日患者さん5人でトランプをして過ごしています>
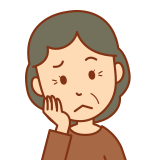
疲れている日もあるんだけど、
トランプに誘われると参加しないといけないと思って参加してしまいます。

たしかに誘われたことを断るのは勇気がいりますよね。
一緒にトランプをしている患者さんに、疲れていることを言えましたか?
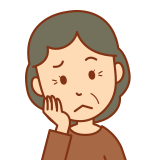
いいえ、言えてません。

一度、調子が悪いと言ってみるのはどうですか?
参加したくない、というのは言いづらいかもしれないですが、
体調がすぐれないんだよね、と相談する感じで。
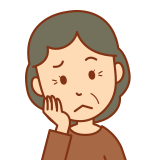
分かりました。
今度言ってみます。
<後日>
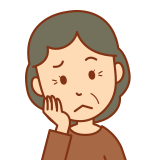
この間言ってみたら、
○○さんの方(一緒にトランプをしている患者さん)から少し休んできたら?と言ってもらえました。

ゆっくり休めました?
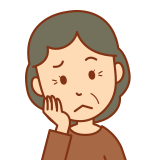
はい、休めました。

それはよかったです。
次からは少しステップアップして休んできてもいい?と言えるようにしてみましょうか。
こんな感じで段階を踏みながら、問題点を解決していきます。
うまくいっているようにみえますが、
”トランプの参加を断れない”
という話は心理士さんから話を聞いて初めて知りました。
受け持ち患者さんだったにも関わらず、Aさんにとって私は相談できる相手ではなかった、
相談しやすい関係作りができていなかったんだな、とこの時気づいたのです。
退院後の生活をともに考える

病棟での療養生活で困難がなくなった段階にくると、退院後について話し合っていきます。
退院後に起こりうる問題を抽出し、
ともに考え
解決策を見つけます
看護師だけでなく、
医師やソーシャルワーカー、心理士などの他職種とも協働するのもポイントです。
退院後に訪問看護が入る場合などは、関係者会議を開催することもあります。
ただし、焦りは禁物です。
退院の話を進めていくことで、
「はやく良くならないと」
「みんなに迷惑をかけている」
と無理をして頑張ろうとしてしまうことがあります。
もちろん、そのような気持ちが生じてしまうことも十分わかります。
看護師はその気持ちを理解しながら、
焦らずに少しずつ回復していくことが完治への一番の近道であることを繰り返し伝えていきましょう
私もうつ病の患者さんの退院支援をした際は、他の看護スタッフとも情報共有しながら慎重にすすめました。
患者さんには
①無理をしないこと
②少しでも体がスッキリしないときは退院について考えなくて良いこと
③悩みや不安があれば話しやすい人に話してほしいこと
この3点はくどいと思われるくらい何度も繰り返し伝えていました。
家族(職場・学校など)に説明する

回復期の患者さんの様子を見た家族は、
急性期に比べて随分よくなったと思うはずです。
そのため、よくなった患者さんの姿を見て、
つい激励したりプレッシャーをかけたりする場合も少なくありません。
悪気があってやっているわけではなく、本人のことを思って関わっていることがほとんどです。
看護師は家族(や周囲の人)がどう本人と関わっているかも重要な観察項目になっていきます。
(高圧的、批判的、攻撃的、干渉的…等)
患者さんの回復には、
適切な家族の協力が必要不可欠になります。
そのため、看護師は関わり方を否定するのではなく、気持ちを受け入れたうえで、患者さんへの理解が深まるように説明していきます。
必要に応じて家族教室などの参加を提案することもあります。
さらに、家族だけでなく、患者さんを取り巻く環境(職場や学校など)の理解を得られるような準備も必要です。
自殺への注意

心がまだうつ状態にあっても身体的な回復が得られ、自殺に対するエネルギーが生まれてくる回復期が最も危険だと言われています。
“嵐の前の静けさ”という言葉がぴったりなように、自殺の前には穏やかになり、病状が回復したように見えることもあります。
3年間働いてきた中で一度だけ未遂の場面に遭遇したことがありますが、想像を絶するものでした。
もう二度と遭遇したくないと思ったのと同時に、このような行動に移してしまう前に気づけなかった、回避できなかった自分の未熟さも痛感しました。
自殺を回避するための主な看護として、
刃物や紐類など、自殺の手段となるようなものを除去していますが、本当に自殺を考えた方はどんな手段を使ってでも自殺しようとします。
(あえてここに記載することは避けます)
患者さんの行動の変化として
・訴えが急になくなる
・周囲への関心がなくなる
・手紙や写真の整理をし始める
・危険物を隠し持つ
・状況に合わない感謝の言葉を述べる
このような小さなサインを見逃さず、
患者さんのつらい気持ちに寄り添うことが重要です。
私もまだまだ経験がないので、これ以上深く書くことはしません。
まとめ
うつ病の診断からおおよそ3か月以降の回復期での看護介入をまとめます。
◎少しずつできることや行動範囲を拡大していく
◎必要に応じて行動や思考のクセを修正する
◎退院後の生活をともに考える
◎家族への説明、必要に応じて職場・学校などの周囲の人に説明する
◎自殺への注意



コメント