精神科と一般科の仕事内容は違う?精神科ならではの仕事その1
 仕事
仕事
2022.07.08
精神科での看護業務はこのようなイメージがありませんか?
精神科ではみなさんが想像している以上に特殊な看護業務がたくさんあります!
私が精神科で働いてきて、
「この業務は精神科病院ならでは!」
と感じた看護業務についてお話します。
看護学生や転職を考えている看護師の皆さまに少しでも精神科看護師特有の業務を伝えられたら嬉しいです。
精神科特有の業務内容
・閉鎖病棟の認識
・物品の個数管理
・患者の行動制限の把握
・患者の持ち込み物品や危険物の管理
・患者の隔離、拘束対応
・ 不穏患者の対応
・エスケープ(離院)の対応
・作業療法
・病棟看護師による退院前訪問
・ECT(電気けいれん療法)
自分の経験をもとにして、ぱっと思いついただけでも精神科特有の業務がたくさんありました。
考えたらまだまだ細かい業務はたくさんあります。
同じ精神科病院でも、入院されている患者さんの疾病によって業務内容は異なります。
ご了承ください。

ぽむ
記事が長くなってしまうので、
その1、その2で分けて書きます。


閉鎖病棟の認識
精神科病院には
病棟入口に鍵がかかっていない「開放病棟」
鍵がかかっている「閉鎖病棟」
があります。
私が働いていた病院は「閉鎖病棟」のみでした。
病室からナースステーションに戻る際、汚物室に行く際、処置室に行くにも全てにおいて鍵が必要です。
病院スタッフは数種類の鍵を所持しており、使い分けながら日々仕事をします。
鍵は落とさないようにユニフォームに繋げておきます。
鍵を開けたら、開けっ放しにしないでその場ですぐに鍵を閉める。
そしてドアノブをカチャカチャしてきちんと鍵がかかったか確認します。
「業務で必ず鍵を使用する」という認識は一般科で働いている看護師にとっては違和感ありありの業務なのではないでしょうか。


物品の個数管理
物品を使用する前と後の数を厳重に管理しています。
清拭で使用したタオル
検温で使用する体温計
ルートキープで多めにサーフローを持っていった場合は、退室時に全ての物品がトレーに入っているか慎重に確認します。
例えば病室にタオルが落ちていた場合。
一般科の患者さんは「落ちていましたよ」と看護師に教えて下さると思います。
ですが、精神科の患者さんは異食をしたり、そのタオルで縊首してしまうなど、危険行動に発展するケースが多いです。
そのため、一般科病棟に比べて物品の個数管理は厳重に行われています。
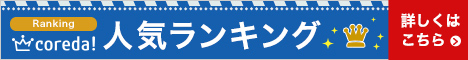

患者の行動制限の把握
そもそも「行動制限」とはなにか。
・外出の可否及び範囲
・面会の可否及び制限
・電話の可否及び制限
これらの行動が主治医の指示のもと決められています。
患者さんの精神症状によって行動制限は変化します。
「電話できないなんてかわいそう!」
「面会できないなんてありえるの?」
私も最初はそう思いましたが、これらの行動制限は効果的に治療を進めるために大切だということを学びました。
少しイメージがつきにくいと思うので、行動制限の「電話」で例を挙げてみます。
電話可の場合(特に制限なし)
患者Aさん(男性)は時々姉に電話をかけます。
足りない生活用品を依頼するためです。
しかし、だんだんAさんの精神状態が悪くなり、姉への電話の回数が増えていくのです。
ある日、お姉さんから看護師に下記のような相談がありました。
Aからの電話がかなり頻回です。
内容も理解できないし、怖くて…。
なんとかならないですか?
Nさんの電話内容を確認すると妄想内容の電話でした。
(普段患者さんの電話は聞いていません)

患者Aさん

患者Aさん
電話の口調も荒く、妄想の修正は困難でした。
この旨を主治医に報告し、診察へ。
診察後、Nさんの行動制限が「電話不可」に変更されました。
精神症状をみながら、主治医が再度行動制限を決定します。
「電話可能」になったり、段階的に制限を緩めたり。
判断は主治医が行います。
このように行動制限は医師の指示のもと行われており、看護師はこの指示を毎回確認しています。
面会の場合
「母はOKだけど父は単独面会不可能」
など条件があることもあるので、しっかり電子カルテで確認しなければなりません。
行動制限はあくまでも医師の指示ですが、
患者さんの病棟の様子を観察し、アセスメントして行動制限について医師に打診していくことも看護師の役割です。
このような行動制限に関する看護は精神科特有ですよね。
患者の持ち込み物品や危険物の管理
精神科の患者さんは自傷、他害のリスクが高いです。
そのため病棟に持ち込める物品に制限があります。
特にハサミや剃刀、爪切りなどの危険物は持ち込むことができないため、病棟で貸し出しを行っています。
他にも靴紐やベルトなどの紐類も禁止です。

ぽむ
入院時にはボディチェックを行います。
入院患者さんが紐の付いたズボンを履いていたとします。
こんな時どうしたらいいでしょうか?
この場合、本人や家族に確認したのち紐を抜いてからズボンを履いて頂きます。
もしくは紐のないズボンへの履き替えをお願いしています。
これくらい大丈夫かな?の気持ちが大きな事故を引き起こします。
特に入院時は本人や家族の前で、持ち込み物品を全てチェックします。
一般科では持ち込み物品にここまで神経質にならないと思うので、これも精神科ならではの仕事だと思います。


患者の隔離、拘束対応
精神科病院では保護室というものが存在します。
また、身体拘束の機会は一般科病棟より精神科の方が多いでしょう。
隔離及び身体拘束に関してはこちらの記事内
「身体拘束・隔離処遇の患者さんへの対応」
という項目に説明がありますのでご確認ください。
私の働いていた病院では毎朝「隔離拘束カンファレンス」というものがありました。
名前の通り、隔離や拘束の指示がある患者さんについてスタッフ同士でカンファレンスをします。
・隔離や拘束をして何日目になるのか
・隔離や拘束条件の確認
・前日の日勤帯や夜勤帯の患者さんの精神状態
・本日勤帯での看護計画
・隔離や拘束が解除できそうか
これらをメインに話していきます。
隔離や拘束は患者さんの治療に不可欠であるため行われる対応です。
しかし、この対応は同時に患者さんの自由や尊厳を奪ってしまう行為でもあります。
そのため、看護師は隔離や拘束をできるかぎり最小限で行えるように看護計画を立案したり、必要以上に隔離・拘束をしていないか日々カンファレンスしています。
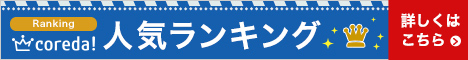

まとめ
精神科ならではの仕事内容~その1~
・閉鎖病棟の認識
・物品の個数管理
・患者の行動制限の把握
・患者の持ち込み物品や危険物の管理
・患者の隔離、拘束対応
その2の記事も書いている途中なのでお待ちください。
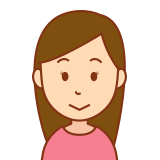
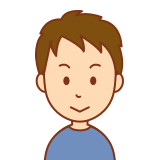







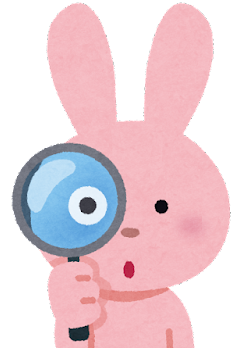
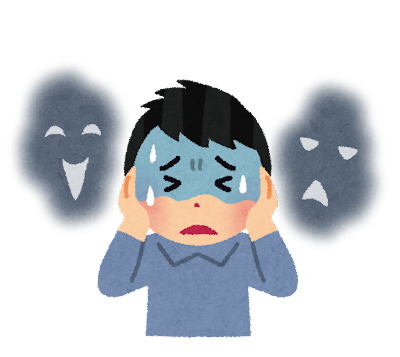


コメント